ショートステイ
2025-04-16
転記作業の大幅削減で業務を効率化し、現場へのフォローを充足。サービスと稼働率の向上を実現

- 施設名:
- 特別養護老人ホーム アットホーム福岡
- 所在地:
- 福岡市博多区千代1-1-55
- ベッド数:
- 18
- 相談員数:
- 2
- 施設名:
- 特別養護老人ホーム 博多の森
- 所在地:
- 福岡市博多区大字下月隈73-1
- ベッド数:
- 27
- 相談員数:
- 2
- 施設名:
- 特別養護老人ホーム アットホーム諸岡
- 所在地:
- 福岡市博多区諸岡2-13-32
- ベッド数:
- 10
- 相談員数:
- 2
- 施設名:
- 特別養護老人ホーム アットホーム板付
- 所在地:
- 福岡市博多区板付6-1-17
- ベッド数:
- 11
- 相談員数:
- 1
- 課題
- 介護ソフトへの転記作業、事業所間での情報共有
目次
転記作業を減らして現場へのフォローに入りたかった
ペースノートの利用状況を教えてください。
当法人は私が所属するアットホーム福岡を含め、4つの施設でショートステイを提供しています。ペースノートはすべてのショートステイの施設で利用しており、予約管理に関わる相談員がメインで利用しています。
ペースノートの導入前、どのように予約管理をしていましたか?
ずっと前から介護ソフトはケアカルテを利用しており、IT化には積極的でした。
ただ予約管理に関してはエクセルで行っており、エクセルに入力した情報をケアカルテに転記する作業がとても手間になっていました。
転記作業はどのくらい発生していたのでしょうか?
当施設は予約や居室の変更が月に100件以上と多く、かなりの業務負担になっていました。
ショートステイは18床と大きくはないのですが、現場職員やご利用者のことを考えて居室の組み換えを積極的に行っていたこともあり、変更が多かったんですよね。
また利用率への意識が高かったので、キャンセルが出れば営業活動を行っていました。幸い利用が決まることが多かったのですが、その場合はキャンセルと新規のスケジュール2名分の操作が2回必要になります。
管理するものが2つになるので、どうしてもミスが起きる確率も高くなってしまいます。
特にこちらの施設は相談員が2名体制なので、エクセルとケアカルテの差異に気づいたときにどちらが正しいか判断がつかないということもありました。
その場合ご家族やケアマネに確認するほかなく、時間がかかるだけでなく不信感にもつながってしまいます。
エクセルファイルはどのように管理されていたのでしょうか?
施設内の共有フォルダに保管していました。
居室の情報も見る必要があるため、現場職員も含めて閲覧をしていました。
エクセルだと一つのパソコンで開いていると他のパソコンで編集することができません。
現場でファイルが開きっぱなしになっている場合は、いちいち電話連絡をしてファイルを閉じてもらわないといけません。お互いに悪気はないですし、電話連絡の時間もかかる上に、一度業務を中断して電話に出ないといけません。
数式やマクロなどはなく、管理しやすい状況だったにも関わらずこういった課題が起きていたので、複雑な管理をしているとなおさらたいへんだと思います。
複数の相談員、現場職員など関わる人数が多い分たいへんそうですね。
そうですね、誰かが間違えて操作をしてしまうと正しいデータとなっていないおそれもあります。
不安があったので手元にバックアップを取ったりもしていたのですが、手間がかかるので毎日できる作業ではありません。少し怪しい時はバックアップをさかのぼるのですが、こういう時に限ってバックアップを取ったのが少し前だったりします。
ファイルが破損する可能性もありますし、保存を忘れると最新版にならないなど管理の課題は尽きませんでした。
また共有フォルダは各施設で独立していたので、施設外から見ることができませんでした。今思い返すとここにも課題がありました。
こちらでショートステイの受け入れができない場合、法人内の他の施設で受け入れができるかどうかの電話確認が必要でした。距離が近いのでこういった運用も可能なのですが、回答に時間がかかることで別の事業所での利用が決まってしまうこともありました。

経営会議でのプレゼンを通じて全施設での導入が決定
エクセルのファイル管理の課題はいつ頃から意識されていたのでしょうか?
3年ほど前に相談員として入職して以来、ずっと改善したいと思っていました。
予約管理を起点にケアカルテや食事箋、送迎表などかなり多くの転記作業が発生していましたが、すべて相談員の業務でした。
ただピンポイントで解決できるサービスが見当たらず、ずっと悩んでいました。
課題を感じていた中でペースノートを知ったきっかけを教えてください。
ケアカルテを提供するケアコネクトジャパンさんが主催するセミナーで、ペースノートさんが登壇されていたのがきっかけです。
メールで案内が届いたのですが、テーマが「ショートステイの業務改善」だったので、聞くしかないと思い聴講しました。
セミナーでペースノートを初めて見た時の率直な印象を教えてください。
「もうこれ!」と思ったのが第一印象です。ショートステイの業務効率の課題は明確だった上に、ケアカルテと連動するならさらに業務改善ができることが想像できました。
セミナーをご覧いただいたあと、どのように上申を進めたのでしょうか?
セミナーの視聴後すぐに資料請求を行い、より詳しい情報をいただきました。
ちょうどセミナーの数カ月後に福岡で介護業界の展示会があり、ペースノートさんが出展されていることを知ったので、管理職ともう一名の相談員で詳しい説明を受けに行きました。
そこでデモ画面を見ることでよりイメージがつきました。セミナーで見た以上に操作感がよく、ペースノートはスケジュールをクリックして引っ張るだけで完結します。
その他の作業も含め、マウス一つで操作ができると思ったのがいいですね。もう一名の相談員も同様に「これはいいね」という反応でした。
ただ導入となると、理事長決裁が必要なので、しっかりと準備を進めました。法人内の委員会で各施設長と相談員、経営層が集まる機会があったので、そこで直接プレゼンを行いました。
準備したおかげか反応もよく、せっかく利用するなら全施設で利用した方が効果があるということになりました。
ちょうど新しく施設ができる予定で、エクセルのファイル管理が不便になることが想定されていたので、いいタイミングでした。

ケアカルテ連携による転記作業の大幅削減
ペースノートの導入によって課題の解決につながりましたでしょうか?
まずはケアカルテ連携の機能を使って転記作業が丸々なくなったことで、かなりの業務効率化につながりました。
ペースノートだけをしっかりと管理すればいいと思えるようになり、今ではケアカルテの予約管理を見ることはほとんどありません。
請求業務でも地味に助かっているのですが、今までと違って送迎のありなしなどの間違いに気付いてもペースノートだけを直せばいいとなりました。
特養の空床利用の請求時にも役立っています。これまでは特養とショートの方どちらにお部屋代を請求するかの判断が、非常に煩雑でした。
ペースノートで空床の枠を設定しておけば、ショートの予約を入れることができ、自動でケアカルテにも連携されます。そのため、特養の方の外泊加算、自費の部屋代のみを確認すればよくなりました。
特養の空床利用とFAX機能の活用による稼働率の向上
以前より意識されていたので稼働率が高かったと思うのですが、導入後さらに向上しました。こちらの要因を伺えますか?
実はペースノートの導入3ヶ月後くらいから稼働率が向上し始めたんですよね。
特養の空床利用も含めて、ペースノートは空いている部屋を一覧で確認できるため、意識しやすくなって行動が変わりました。やはりお部屋が空いていると予約を埋めようと思いますし、ショートが空いていないからとお断りするのではなく、「そういえば特養が空いてたな」と思い出せます。
エクセルで空床の把握をがんばっていた時期があったのですが、やはり手間がかかっていたのでなかなか徹底はできていませんでした。
特養の空床利用をさらに活用できるようになったんですね。
そうですね、空床の把握だけではなく、ペースノートで効率化できた分、現場に行ける時間が増しました。特養として利用されていたお部屋のお荷物の整理や、ご説明などに時間を使っています。
特養ユニットの職員はショートステイのご利用者に慣れている訳ではないので、相談員の協力が不可欠です。
ご利用者ごとに過去の履歴も見れるので、「この方だと特養ユニットでも大丈夫かな」といった把握もできます。特養に比べるとショートの利用者は要介護度が低く、社交的な方だとどうしても手持ち無沙汰になり、再度使ってもらえる確率も下がってしまうので配慮が必要です。
相談に来られたケアマネさんにも事前に特養の空床利用であればという条件を伝えておくことで期待値のコントロールがしやすいです。
体感としては6割程度はお断りされるのですが、ショートのユニットを気に入ってくれてるご利用者が多いことの裏返しだと思います。
FAX送信は稼働率に影響していますか?
めちゃくちゃ助かっていますね。
以前も複合機に登録した事業所に50件ほどお送りをしていたのですが、新しい事業所を登録するのがたいへんで、なかなか数を増やせていませんでした。
導入前にペースノートさんが近隣の事業所リストを作成してくれるので、送付先が200件まで増えました。
たまたまですが、違う区で働いていたので、昔のご縁でお返事をいただけることもありました。「ちょっと遠いけれど来てくれる?」といった感じで相談を受けるので、範囲を増やして正解でした。
あとはFAXを送付する際に、空床の日付を自動で一覧化してくれるのも業務負担が少なくていいですね。おかげさまで一度向上した稼働率は今でもキープできています。
お問い合わせ管理の機能も活用されていますよね。
はい、お問い合わせ管理の機能もかなり活用しています。当施設は相談員が2名でシフト制のため、1人しかいない日が出てしまいます。ですので情報共有の重要度が高くなってきます。
以前は運用の工夫として、ケアカルテにダミーの利用者情報をつくり、そこに全員分の問い合わせをまとめて入力して情報を共有していました。
今ではご利用者ごとにお問い合わせを記録できるので、格段に情報共有がしやすくなりました。
面談のステータス登録もできるので、面談済みの方は省くことができるのもいいですね。
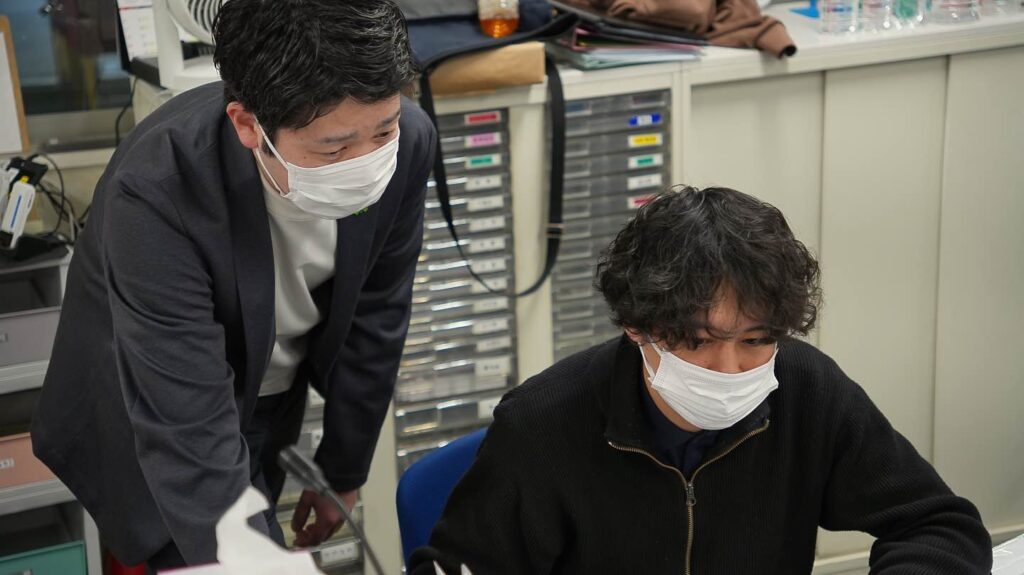
機能改善を通じて介護業界を一緒に盛り上げていく関係性に
予想外だった導入効果はありますでしょうか?
クラウドのシステムなので、外からでも利用できるのがいいです。訪問で追加の相談を受けた時など、その場で空床状況を確認して回答できるのが助かっています。
あとは使っていく中で、予約を表すラインに色付けできることがいいと気付きました。このような予約管理に関する細やかな機能も行き届いているので、本当に便利です。
あとは稼働率が常に表示されるのもすごくいいですね。やはりずっと目に入ると「なんとかいい数値に持っていきたい」と思います。
エクセルでもファイルを分けて稼働率の管理はしていましたが、ペースノートはトップ画面に自動で算出されるから手間なく意識できるようになりました。
空床利用と分けて表示されることもすごくいいですね。どのくらい空床利用ができているかの分析もできるようになりました。
法人内の他施設の数字も見れるのですが、おそらくどの相談員も負けていられないという気持ちがあるでしょうし、お互いの刺激にもつながっています。
機能以外のご評価はいかがでしょうか?
まずは導入前のサポートがとても厚く、初期登録の手間がなかったのですぐに使い始めれました。
オンラインのサポートに関してもとても早くて助かりますね。特に当法人は複数施設あるのですが、オンラインだとまとめてペースノートさんのお話が聞けます。
私が導入を推進していたので、どうしても他の施設と温度差があることも想定されていました。全施設が同じ説明を受けることでその温度差が目に見えて、他施設のサポートがしやすかったです。
また、介護ソフトは今ある機能をなんとかして使うものという印象があって、その心づもりで導入しました。
しかし利用してみると、とても早いスパンで機能が開発されていて、本当に尊敬しています。
今回も取材で訪問いただいたにも関わらず、新機能のご提案をいただきました。今では導入時よりもいいものになっているので、こういったところも大事な観点だと思います。

これから導入を検討されている方にアドバイスがあれば教えてください。
生活相談員はなんでも屋になりがちですが、裏を返せばなんでもできる職種だと思います。
なので相談員の業務改善は施設運営に直結しますし、施設の必要なところに手を回すことができます。
実際に、ペースノートのおかげで空いた時間を使って、医療連携の加算の取得につながり、ショートの稼働以外の部分でも収益の改善につなげることができました。医療機関との定例会議に相談員が入る必要があるので、どうしても時間が必要になりますからね。
現場のフォローに入る方も多いと思いますが、やはりこちらも時間がないとできないことです。
今後の展望や期待はありますか?
使っていく中で気になる点を伝えると、さらに使いやすくなっていく実感があります。
機能改善がご利用者や施設運営に還元できているので、これからも一緒に介護業界を盛り上げていける関係性でいれると、たいへんうれしく思います



